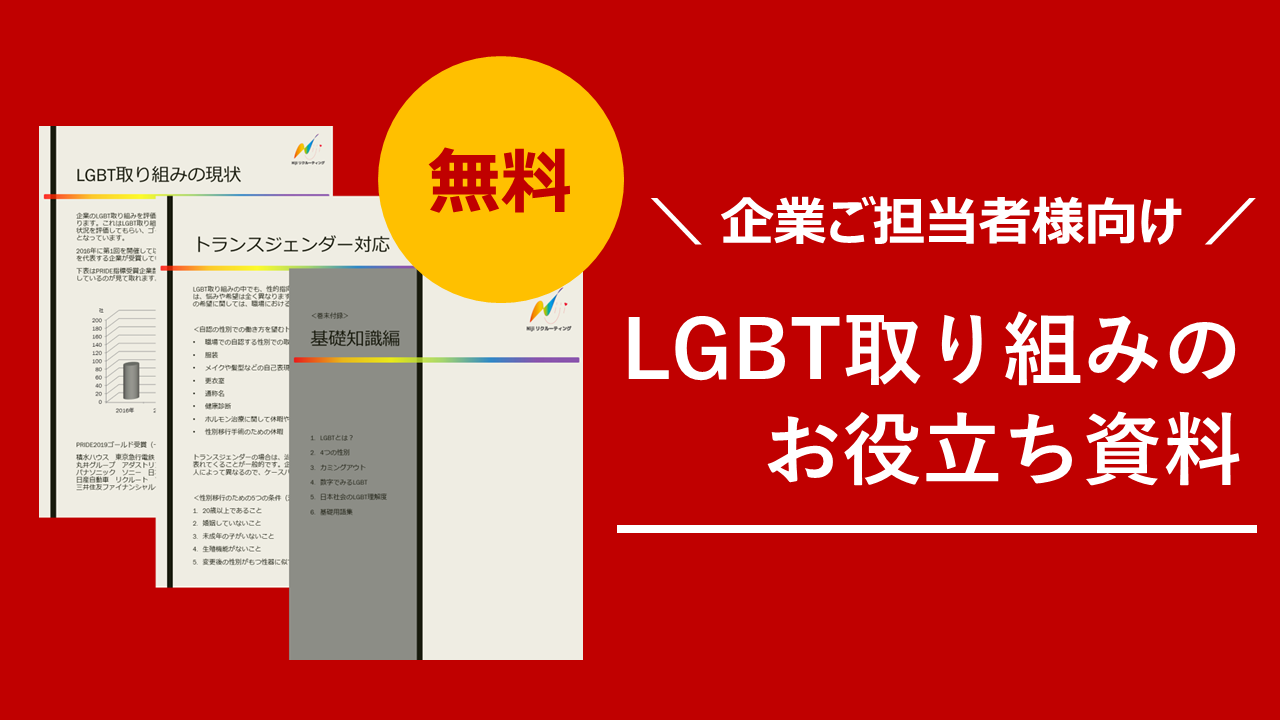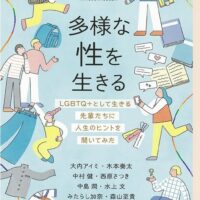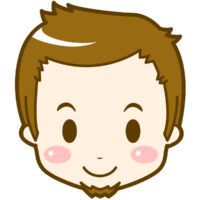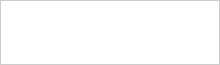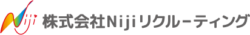採用に関して、厚生労働省から「公正な採用選考の基本」という考えが示されており、そこには性的マイノリティなど特定の人を排除しないようにということが明記されております。
また性的指向や性自認を理由に、不採用とすることは採用差別に該当すると考えられます。
このような社会情勢を受けて、採用面接においてLGBT求職者に適切な対応をとれるようにと、研修などを実施する企業が増えております。
一方で、実際の対応経験が少ないために、適切な対応が分からないという人事部の声もあります。
今回は、採用面接の場面でよく言われる基本的な対応をもう一歩、深堀して、“実務”において知っておきたいLGBT対応についてご紹介します。
- 履歴書(エントリーシート)の性別欄の見直し
採用面接におけるLGBT対応というと、まっさきに上がる項目が履歴書(エントリーシート)の性別欄の見直しです。
これに関しては、見直してほしいというLGBT(という表現は不正確。トランスジェンダーやXジェンダー、ノンバイナリー、クエスチョニングなど)の求職者からの声が多くあります。
また企業の人事部としても手を付けやすい項目なので、最も対応が進んでいる取り組みの一つです。
この対応により応募しやすくなったという求職者もいます。
しかし、これは一般的なアンケートの性別欄のような一時的な話とは異なり、応募、その後の面接、入社、入社後の職場という永続的な話になります。
そのため入り口段階である履歴書の性別欄の見直し対応だけでは、あまり問題は解決せず不十分と言えます。
性別欄の見直し自体はしても良いとは思いますが、本来は入社後の(自認性での)働きやすさの対応も含めて、実施していくことが必要になります。
- カミングアウトを受けた場合はアウティングに注意
面接の場でカミングアウトを受けることがあります。
その際には、アウティングをしないように、採用チームへの情報共有は慎重にすべきという考えがあります。
これは本当にその通りです。アウティングは不可逆的な行為であり、パワハラ防止法においても求職者に対するアウティングもパワハラに該当する可能性があると考えられます。
ただし、アウティングを避けるという意識と同時に、採用チームで情報共有をする大切さも考えることが大切です。
採用面接の場でのカミングアウトは、基本的には何か具体的な希望があるケースが多いです。
その場合は、求職者側も採用チーム(人事部)での情報共有を想定(期待)していることも多いです。
アウティングは論外ですが、アウティングを意識し過ぎて情報共有しないことも良いとは限りません。
求職者にとって何度もカミングアウトを強いられることも負担につながります。
カミングアウトを受けた場合には、アウティングへの留意が必要なのは当然ですが、同時に情報共有の必要性をしっかり求職者に伝えて、情報共有の同意をとることも大切です。
- 入社後の対応は求職者の希望にできるだけ沿う
採用面接において、求職者からカミングアウトを受けると同時に、働く上での希望を受ける場合があるのは前述の通りです。
希望を聞いた場合には、基本的にその希望に沿った対応ができるのが良いです。
ただし、求職者の希望に沿うことが最善と言えないケースも多くあります。
求職者はさまざまな理由から、自分の希望をしっかりと面接の場で伝えられないことが少なからずあります。
求職者は職場の設備や働き方、風土なども分からないので、希望が分からないということもあります。
さらに、入社後に希望が変わるということもよくあります。
基本的には求職者の希望に応えることが良いのですが、それだけではないということを覚えておいていただくと良いと思います。
Nijiリクルーティングでは、日頃、LGBTの求職者と企業の採用担当者の間にたって、両者の声を別々に聞く機会が多くあります。
今回は、そのときに感じるギャップについてご紹介しました。
採用担当者は、まずは基本的な対応を抑えることが最重要ですが、もう少し余裕ができたら、上記のような点も知っておくことも、実務的には大切だと感じています。