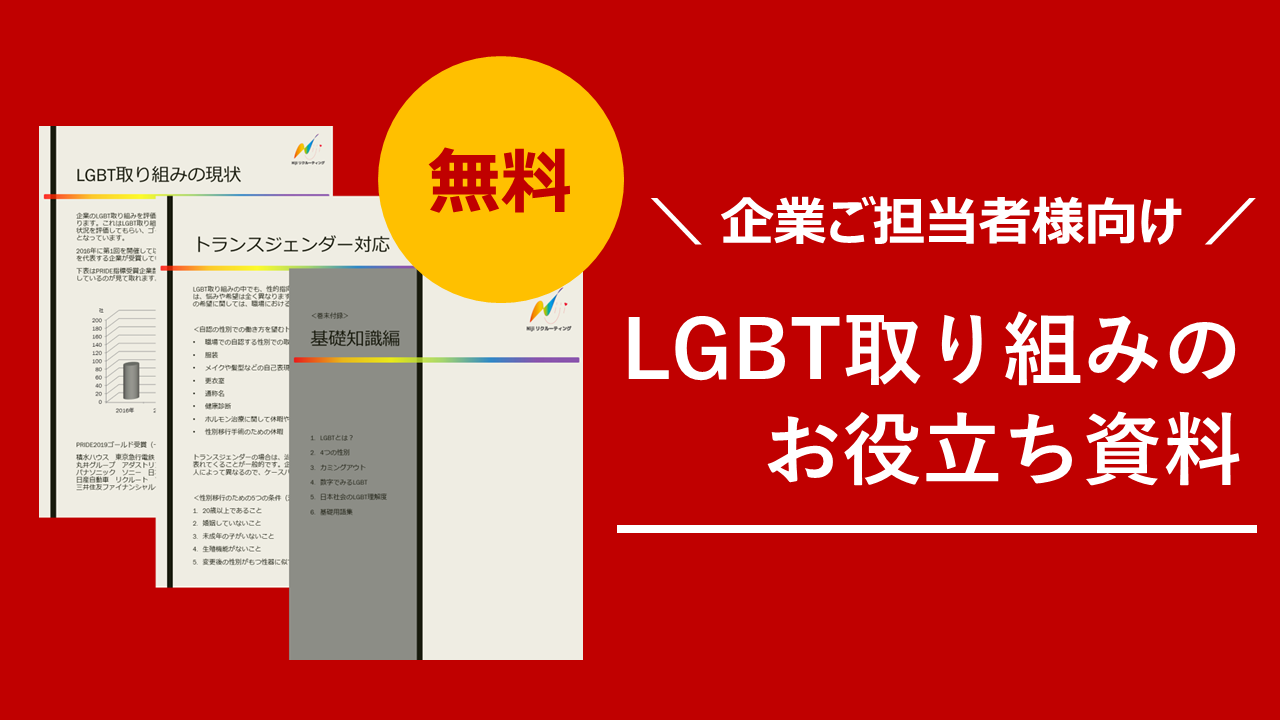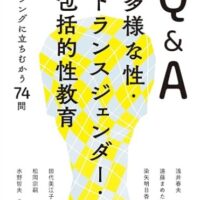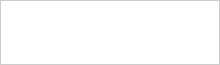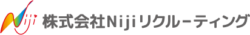『LGBTのコモン・センス』
山形大学教授で法哲学者の池田弘乃氏による著作です。
さまざまなセクシュアリティの当事者へのインタビューから始まり、性のあり方や法制度まだ幅広く取り上げられています。
2024年6月に刊行されているので、比較的新しい話題まで組み込まれています。
本書は『LGBTのコモン・センス』というタイトルですが、LGBTについての常識を読者に教え諭そうとするのではなく、常識をもう一度、考え直そうというスタンスで書かれています。
そのため一つの考えを押しつける感じはなく、さまざまな角度や視点の意見も書かれているので、内容が自然に頭に入りやすいです。
平易な文章で書かれているのもあって読みやすいので、LGBTという言葉は知っていて、もう少し知りたい、興味がある、という読者にはとてもおススメの一冊です。
書籍概要
ジェンダー・セクシュアリティと法制度の関わりを研究する著者が、LGBTという言葉を手がかりに、多様な性に関する常識の編み直しを試みる。
本書の第1部では、多様な性を生きる人々の生活を描くことを通じて、当事者の声から私たちの社会を見直すためのヒントを探っていく。
第2部では、全ての人が「個人として尊重」される社会を展望していくために、多様な性に関わる言葉について整理し、日本社会の現時点での課題について考察する。
補章では、「多様な性」理解増進法についての対談も収録。
いかなる性を生きる人も「個人として尊重」され、安心して暮らしていくために、この社会に必要とされているのは何かを考察する一書。
目次
第一部 わたしたちはここにいる
第一章 相方と仲間―パートナーとコミュニティ
第二章 好きな女性と暮らすことーウーマン・リブ、ウーマン・ラブ
第三章 フツーをつくる、フツーを超えるートランスジェンダーの生活と意見
第四章 社会の障壁を超える旅―ゆっくり急ぐ
第二部 全ての個人の尊厳に向けて
第五章 多様な性を考えるための言葉
第六章 日本社会の課題と展望
印象的なコンテンツ
『苦しかったねぇ。私はそのことに関して全く知識がないの。知っていきたい』(P47)
インタビューに登場する福美さん(レズビアン)が知人にカミングアウトをしたときの反応です。
ちゃんと受け止めてもらえる期待はあまりなかったのですが、意外にもこの知人は、カミングアウトを受けたその足で、最寄りの本屋にいって関連する本を買って“知る”ことからはじめ、『福美さんのような人を支える人間になりたい。興味本位ではなく、いろいろなことをちゃんと知っていきたい』と伝えます。
福美さんがパートナーと一緒に暮らすことになったときも『お嫁さんに行くんだね。』と祝福とともに送り出してくれます。
著者は“お嫁にいく”という表現の古くささを指摘しつつも、言葉尻を問題にするのではなく、祝福の気持ちを肯定的にとらえています。
『いえ、そうおっしゃっても、身体を変えないと、しずかさんと結婚できないんです』(P72)
トランス男性のたくやさんが、結婚相手のしずかさんのご両親に『結婚より、たくやさんの身体のほうが大事だ』と心配されて言われたときの、反応です。
戸籍の性別変更には、性別適合手術が必須だったので、やむなく手術を受けることにします。
第四章で紹介される、トランス女性の美奈さんは、自身も性別適合手術をうけており、同時にこの性同一性障害特例法に定める手術要件に関しても肯定的に考えています。
本書ではこの手術要件に関しては、『当事者他によるものも含め実にさまざまな議論がある』と紹介されています。
『人々は、互いの性について意識する(される)ことなく、生活上のやり取りをしていることも多いだろう』(P126)
著者は、これを社会生活上の性別として説明しています。
社会生活上の性別は性表現にも近いのですが、周囲もその性別を受け入れているかどうかという点に違いがあるように感じます。
性別で区別される設備等を使用する際には、性自認よりも、この社会生活上の性別がより重要になってきます。
感じたこと
本書では、補章としてLGBT理解増進法についても、ページを割いて説明&国会議員(超党派LGBT議連事務局長の谷合氏)との対談を載せています。
LGBT理解増進法については、否定的な意見を多く目にすることが多いのですが、肯定的にとらえているのも本書の特徴の一つです。
企業や職場に直接関連する話は少なく、またいわゆる知識的な話は少ないですが、職場での理解を深めるための前提となるLGBT(やセクシュアリティ)という言葉や存在をちゃんと(バランスよく)理解できる良書なので、職場でもおススメです。