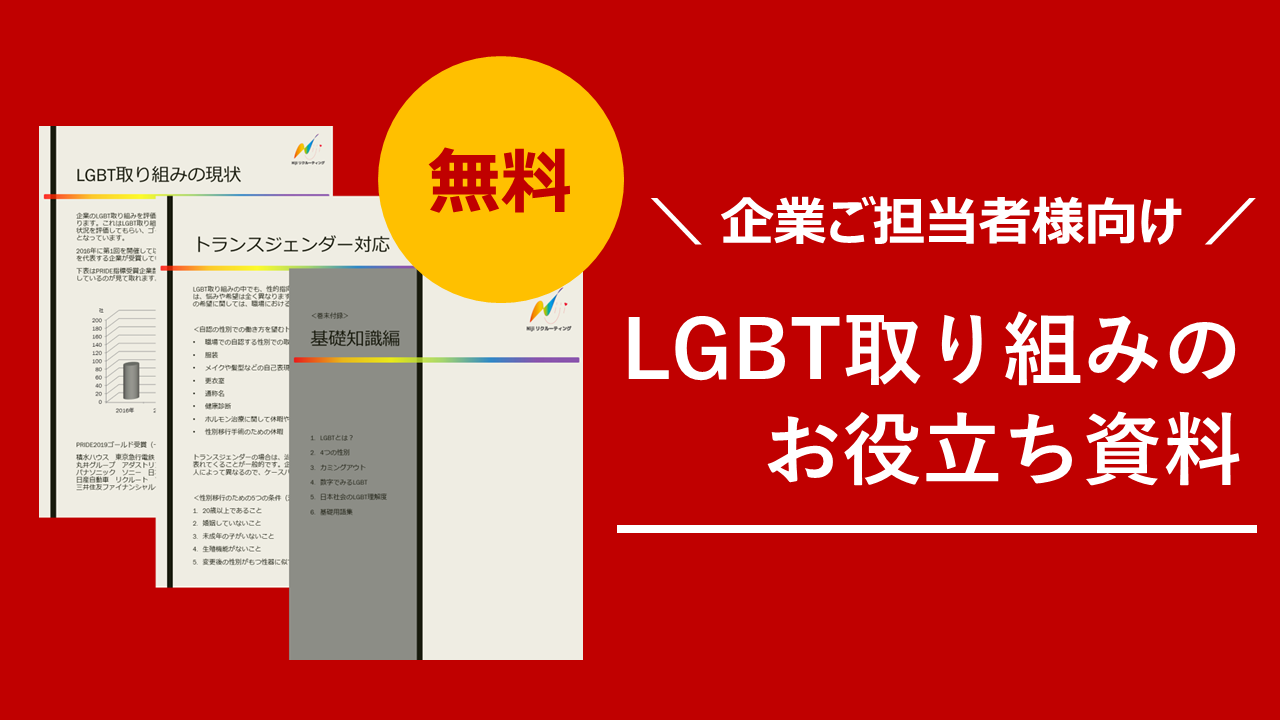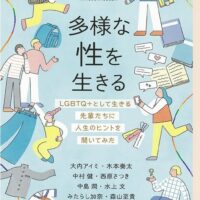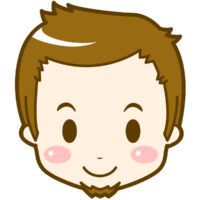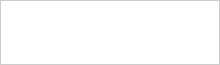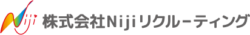6月は「PRIDE月間(Pride Month)」として、世界中でLGBTへの理解と支援を示す様々なイベントやキャンペーンが展開されます。
企業にとっても、多様性と包摂(ダイバーシティ&インクルージョン)を推進する重要な機会です。
今回は人事担当者の皆様が今後の施策立案に活かせるように、企業がPRIDE月間に実施した啓発活動の具体事例を5つ紹介します。
PRIDE月間とは?
PRIDE月間とは、LGBTの権利向上と尊厳を称える月間で、毎年6月に世界各地で実施されています。
その起源は1969年6月、アメリカ・ニューヨークで発生した「ストーンウォールの反乱」にあります。
この事件をきっかけに、LGBT当事者による権利獲得運動が本格化し、以後6月は多様性を祝福する月として定着しました。
PRIDE月間では、LGBT当事者によるイベントも数多くありますが、最近では企業においても、啓発月間として取り組みをする事例が増えています。
事例1:LGBT関連商品の販売と寄付
A社(アパレル企業)では、PRIDE月間限定でレインボーカラーをモチーフにしたTシャツやアクセサリーなどを販売し、売上の一部はLGBT支援団体に寄付されました。
単なる商品開発にとどまらず、商品タグにLGBTの歴史や用語解説を記載することで、消費者への啓発も同時に行う取り組みとなりました。
このような商品展開は、企業の姿勢を消費者にわかりやすく伝える方法として有効です。とくに若年層の顧客層にとって、社会的メッセージを持つブランドは支持されやすい傾向にあります。
事例2:経営トップによる「LGBTアライ宣言」
B社(金融機関)では、社長自らが「アライ(LGBTを支持し共に行動する人)」として声明を発表し、社内外に向けて「誰もが自分らしく働ける職場をつくる」というメッセージを発信しました。
さらに、役員レベルでのダイバーシティ研修も並行して実施され、経営層が率先して理解を深める姿勢が話題となりました。
企業文化の変革には、トップのコミットメントが不可欠です。
特に人事領域では、経営層の本気度が組織全体の取り組みの成否を左右します。
アライ宣言は、取り組みの「旗印」としての機能も果たします。
事例3:社員向けLGBT研修の実施
C社(製造業)では、PRIDE月間に合わせて全社員向けのLGBT基礎研修を実施しました。
内容は、性的指向や性自認の基礎知識から、職場での配慮事項、LGBTに関する無意識バイアスについてなどです。
オンラインでの配信形式とし、受講者の声を可視化することで学習効果を高めました。
このような教育施策は、表面的な理解から一歩進んだ「行動の変容」へとつなげる鍵となります。
加えて、研修を継続的に行うことで「一過性ではない姿勢」が社内に根づいていきます。
事例4:LGBT当事者による社内トークイベント
D社(IT企業)では、PRIDE月間中に当事者社員とアライ社員によるトークイベントを開催しました。
テーマは「自分らしく働くために必要なこと」です。
社内イントラネット上でもイベントの録画を共有し、部署や職種を問わず視聴できる環境を整備しました。
こうした「生の声」を聞く機会は、理論だけでは伝わらない当事者のリアルな体験を共有することができ、共感と理解を深める貴重な機会となります。
社員間の距離が縮まり、風通しの良い企業文化の醸成にもつながります。
事例5:社内環境の可視化と変化
E社(広告業界)ではPRIDE月間に合わせて、社内食堂にレインボーカラーのポスターを掲示し、LGBTに関する基本用語や相談窓口の案内を目立つ場所に配置しました。
また、イントラネットの壁紙や画面バナーもレインボーデザインに変更し、月間中は自然と視界に入るよう工夫されていました。
目に見える工夫は、「企業としての意思表示」となり、当事者にとっても安心感につながります。
あえて大きくアピールすることで、普段話しづらい話題への関心喚起や、当事者が孤立しないためのメッセージとなります。
企業が多様性を尊重する風土を築くうえで、啓発活動は単なるイベントではなく、組織文化を根本から変えていくための重要な手段です。
従業員一人ひとりの意識の変化のためには、LGBTに関する情報に「継続的かつ多様な形で触れる機会」を提供することが欠かせません。
人事部門としては、6月の取り組みをきっかけに、継続的な教育プログラムや制度設計、評価指標の導入など、「仕組み化」による組織改革へつなげる視点が求められます。
PRIDE月間を風土づくりに活用してみてください。