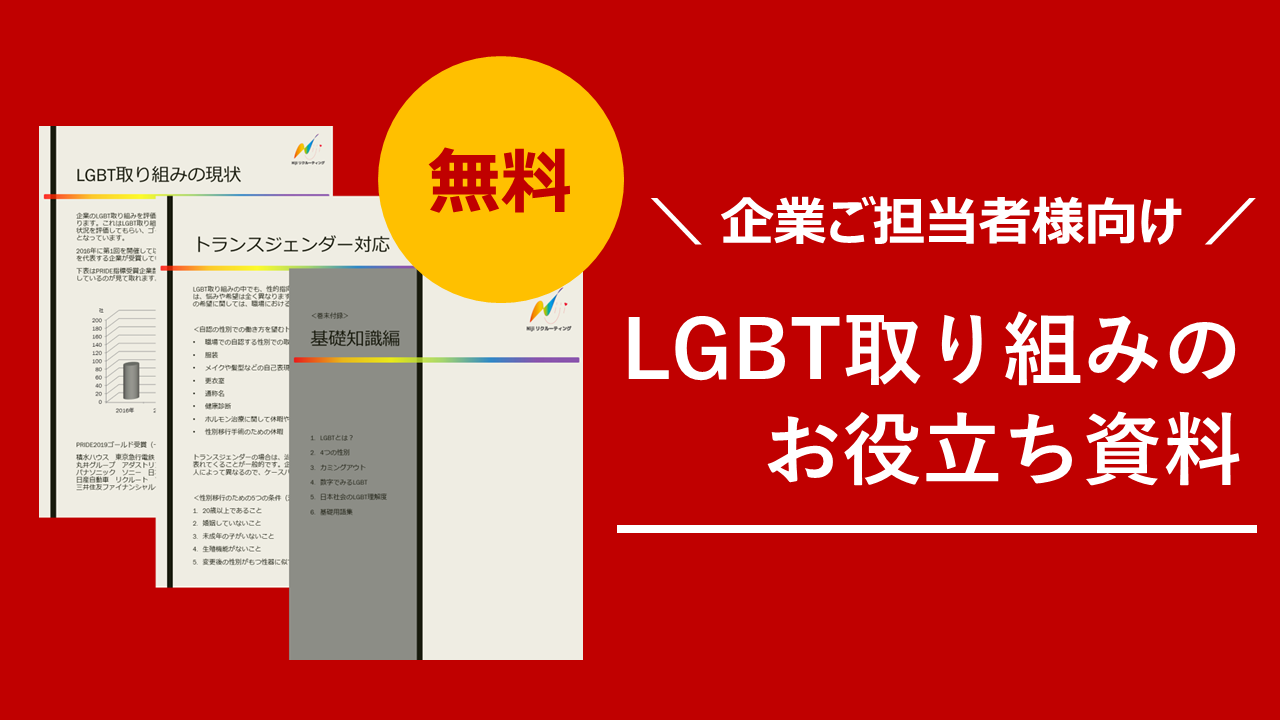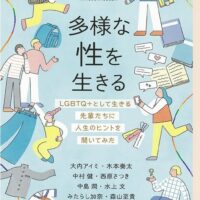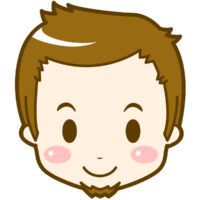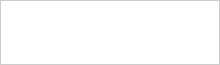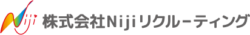この季節、多くの職場では「夏季休暇」や「お盆休み」をめぐる話題が広がります。
旅行や帰省など明るく軽やかな会話のはずが、LGBT当事者にとっては胸がざわつく場面に変わることがあります。
今回は、“夏”だからこその職場での働きづらさについて、LGBT当事者の声をご紹介するとともに、どういう場面で働きづらさにつながるのかを考えてみます。
■ケース1 休暇申請に「パートナー」を理由にできない
夏季休暇の予定を上司に申請するとき、多くの人は「妻と旅行に行く」「子どもを連れて帰省する」と自然に話します。
しかしAさんの場合、旅行の相手が同性のパートナーだと、それを正直に伝えることに大きなためらいがありました。「余計な質問をされるのでは」「妙な目で見られるのでは」と考え、結局「友人と出かけます」と言葉を選び直さざるを得ません。
小さな場面ですが自分を隠さなければならない負担が積み重なります。
■ケース2 帰省前後の話題で取り残される
お盆の時期になると、職場では「実家に帰るの?」という会話が自然と広がります。
トランスジェンダーのBさんは、親にはカミングアウトしているものの、親戚には自分のセクシュアリティを隠しているため、この時期の帰省はずっとしていません。
しかし職場で「帰省しない」と答えると「親と仲悪いの?」と勘違いされます。
素直に話せず、同僚との間に見えない壁を感じてしまいます。
■ケース3 クールビズとジェンダー規範
クールビズが推奨されるこの季節は自由な格好をして良いといわれているのに、実際には暗黙の規範があります。
Cさんはゲイであることを職場に公にしていませんが、好きな服のテイストは一般的な“男性らしさ”から少し外れています。
カラフルなシャツや細身のパンツを着ると、「ずいぶんおしゃれだね」「デートでもあるの?」とからかわれた経験がありました。
それ以来、無難な服しか選べなくなったのです。自由と言われても、その自由は「異性愛的な男性らしさ」の範囲に限られているように感じる、とのことでした。
■ケース4 休暇の調整で感じる不公平
夏季休暇のスケジュール調整では、既婚者や子どもがいる社員が「家族を優先したい」と伝えると、当然のように尊重されます。
しかしDさんが「大事な人と過ごしたい」と言ったとしても、その価値は軽く扱われてしまうような気がします。
制度や文化のなかで「家族」とみなされる人と、そうでない人の間にある見えない線引きがこんな場面でも見られます。
■ケース5 「結婚まだ?」という軽い一言
お盆明けの雑談で、上司に「そろそろ結婚考えないの?」と軽く言われました。
普段はこのような微妙な話題には触れない上司なのですが、親族の中での結婚話を聞いたことがきっかけでの発言だったそうです。
Eさんにとっては答えに窮する問いです。笑ってごまかしても心は沈んだそうです。
夏季休暇・お盆・クールビズといった職場の出来事は、一見ただの季節の風物詩です。
しかしLGBT当事者にとっては、「異性愛・結婚・家族」を前提とする文化や制度が強調され、隠す/ごまかす/合わせるという負担が増す時期でもあります。
つまり”夏”は日本社会の規範が可視化されやすい季節であり、その影響が職場の空気や人間関係に直接反映されるという側面があります。
この可視化されやすい規範は、多くの人にとっては当たり前であり、ポジティブな要素が強いため、そう感じない人がいることに想像が広がりにくいという特色があります。
日常の業務の中では踏み込まないプライベートな領域にも会話が広がっていきやすいからこそ、いろいろな事情や感じ方、過ごし方の人がいるということも頭に入れておくと良いと思います。