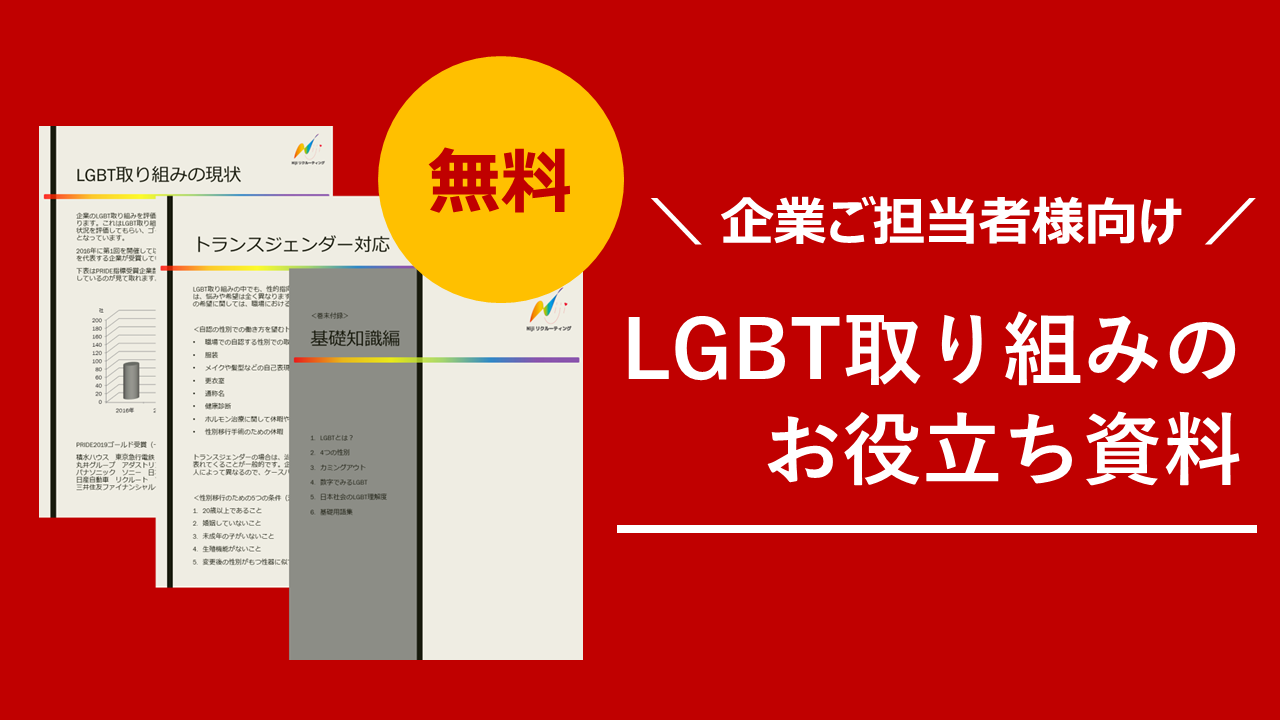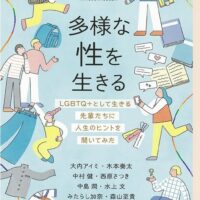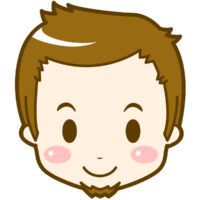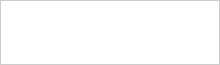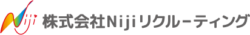『生殖記』
直木賞作家の朝井リョウ氏の最新作です。
ある政治家の『LGBTには生産性がない』という差別的発言が数年前にありましたが、おそらくこの発言を念頭に本書は書かれていると思われます。
朝井氏は前作の“正欲”でも、性的マイノリティをテーマに描いていました。両方に共通するのは、性的マイノリティの生きづらさの根源を描こうとしている点にあると感じます。
本書は、語り手が主人公(ゲイ)の男性器という奇抜な視点がまず目を引きますが、実際にはゲイという主人公の立ち位置を通じて、異性愛者も含めたヒトの生きる意味を言語化し、それにそぐわないからこその生きづらさを描いています。
ストーリー展開は大きくなく、読みにくい部分もあるかもしれませんが、同性愛者の生きにくさをもっと理解したい、自分自身の幸福感を深く考えてみたいという人にはとてもおススメです。
書籍概要
とある家電メーカー総務部勤務の尚成は、同僚と二個体で新宿の量販店に来ています。
体組成計を買うため――ではなく、寿命を効率よく消費するために。
この本は、そんなヒトのオス個体に宿る◯◯目線の、おそらく誰も読んだことのない文字列の集積です。
印象的なコンテンツ
『結論から言えばそれは、子個体による「私は同性愛個体です」という表明は、特に日本に生息する個体にとっては共同体の縮小宣言と同義だからです。
共同体が目指すものを阻害する個体は”悪”と見做されるからです。そして、悪とみなされた個体は、その共同体から追放される恐れがあるからです』(P52-53)
同性愛者が親にカミングアウトをする場合に、なぜ謝るのか?という疑問への答えです。
共同体(≒社会)が目指すものは、『均衡、維持、拡大、発展、成長』だそうです。
『所属している共同体に貢献したいという気持ちが、自分は共同体に所属しているのだという感覚=共同体感覚を強めてくれる。その共同体感覚こそ、人間の幸福度に大きく関わっている。共同体感覚が高いほど、幸福度も高くなる』(P76)
共同体への貢献は生殖だけでなく、労働も貢献になります。労働との相性が悪い個体(人)は、幸福度が高くなりにくいと、されます。
『結婚も特別養子縁組も、これまで同性愛者全員が不可能だったことが、カミングアウトできる環境にいる人から順に可能になる。それは新しい分断を生むとは思っています』(P228)
職場の後輩の颯(そう)の発言です。
颯も同じくゲイですが、職場でもオープンにしており、転職して、NPO活動を始めていきます。
筆者の目線は、同じLGBTQの中の、同じ同性愛者の中の、ゲイの中の違いについて解像度をあげて迫っていきます。
『入浴も排泄も自分で出来ないような今の自分に生産性なんてあるのかと、多くの個体は今後、幸福度を下げていく傾向にあります』(P275)
異性愛者であっても、加齢とともに共同体への貢献ができなくなると幸福度がさがってくるという指摘です。
感じたこと
生殖器が語り手という初手の奇抜さはありますが、本質は、ヒトという種への適当な距離感と客観的な視点の確立にあります。
同性愛者がなぜ共同体(社会)で生きにくいのかという問いへの答えと同時に、それは同性愛者だけでなく、異性愛者にも同じことが言えるということに気づかされます。
自分にとっての幸せな生き方とは何か?共同体のかかわりとどう関係するのか、を考えさせられる一冊です。