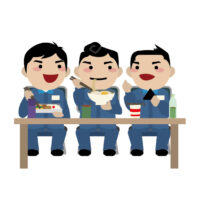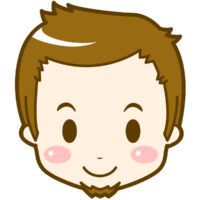近年、多くの企業がLGBTQに関する基礎研修を実施するようになりました。
そこで扱われる内容は、「性的指向と性自認の基礎知識」「各頭文字の意味」「ハラスメントの注意点」など、まずは“知識を入れること”が中心です。
もちろん、この基礎知識は極めて重要です。
しかし、現場で当事者と向き合うと、多くの管理職が「知識は理解したつもりだけれど、実際の対応となると不安がある」と感じています。
どのようにしたら、実際の対応につなげることができるのでしょうか?
LGBTQとは、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー・クエスチョニング(あるいはクィア)を総称する言葉です。
総称であるがゆえに便利であり、社内研修でも教育の出発点として広く用いられています。
しかし、総称であるという点は同時に限界も持っています。L・G・B・T・Qのすべてに該当する人はいませんし、性的指向と性自認は本来まったく異なる視点です。
つまり「LGBTQの人は〜」と語り始めた瞬間に、特定の誰かではなく、漠然とした集合体を指す抽象的な話になってしまいます。
研修においても、「LGBTQという人はいません」「セクシュアリティによって、困りごとや希望は全然違います」という話は必ずしますし、言われれば、そのときは“理解”できます。
しかし、すぐ後の質疑応答では「LGBTQの人は〇〇の場合に~」というような質問がくることがよくあります。
解像度が低いままの理解は、次のステップで行き詰まりやすいです。
「配慮したつもりなのに、当事者には響かなかった」という場面もその一つです。
大きな主語だけで議論を進めると、現場で出会う“個人”との距離が縮まらないのです。
では、基礎研修のあとに企業が取り組むべきことは何でしょうか。
結論から言えば、「一人ひとりの状況に合わせて判断できる現場力」を育てることです。
LGBTQに関する相談の多くは、実際には細やかな文脈の中で生まれます。
例えば、トランスジェンダーの社員がどのタイミングで通称名の使用を希望しているのか、同性パートナーを持つ社員がどこまで職場で関係性を開示したいのか。
これらはマニュアルで一義的に示せるものではなく、本人が望む範囲、職場風土、業務の特性などの要素が複雑に絡み合っています。
つまり、次のステップとは「ケースバイケースに対応できる柔軟な判断力」を組織として持つことです。
そして、それを支えるには以下の3つが鍵になります。
① 主語を意識する
「LGBTQの人は〜」ではなく、「この社員は何を必要としているのか」という視点を軸にするためには、職場全体で主語を意識することが大切です。
これは特別な取り組みではなく、日常会話の中で自然に育てることができます。
たとえば「このケースでは本人にどう確認するのがよいか」「この部署の状況を踏まえると何が選択肢になるか」といった具体的な会話が増えると、主語が自動的に現場に近づきます。
“多様性”という全体を語る言葉から、“目の前の誰か”へと焦点を移すことが、次のフェーズの根幹となります。
② 相談しやすさを左右するのは制度ではなく「風土」
多くの企業で相談窓口や福利厚生など制度整備はかなり進んでいますが、実際に制度が使われるかどうかは、職場風土に大きく左右されます。
「制度はあるけれど、誰も使っていない」という現象は、制度そのものが機能していないのではなく、使うための心理的安全性が確保されていないケースが多いです。
心理的安全性を確保するための手段の一つとして、管理職が個別の相談に対応できるスキルを身につけることも大切です。
ここで重要なのは、管理職自身が“LGBTQに関する知識を完璧にする必要はない”ということです。むしろ重要なのは次の3点です。
- 分からないことを素直に確認できる姿勢
- 本人の希望を尊重しながら、必要な事項を丁寧にヒアリングする力
- 推測や思い込みで対応しないという態度
管理職が“すべてを知っていないといけない”という思い込みを手放すことで、相談の敷居は大きく下がります。
結果として、心理的安全性の高い職場が育ちやすくなります。
③ 当事者の声を“ひとつのモデル”として扱わない
当事者の体験談は理解を深めるために非常に有益ですが、同時に“これがLGBTQの典型例”と捉えないことが大切です。
当事者の語りはあくまで個人の経験であって、すべての当事者を代表するものではありません。
むしろ、複数の異なる声が存在するという前提こそが、次のステップで求められる視点です。
総称としての「LGBTQ」という主語から一歩進み、社員一人ひとりに目を向け丁寧に理解しようとする姿勢こそがダイバーシティ&インクルージョンに求められる本質的な取り組みだと考えます。