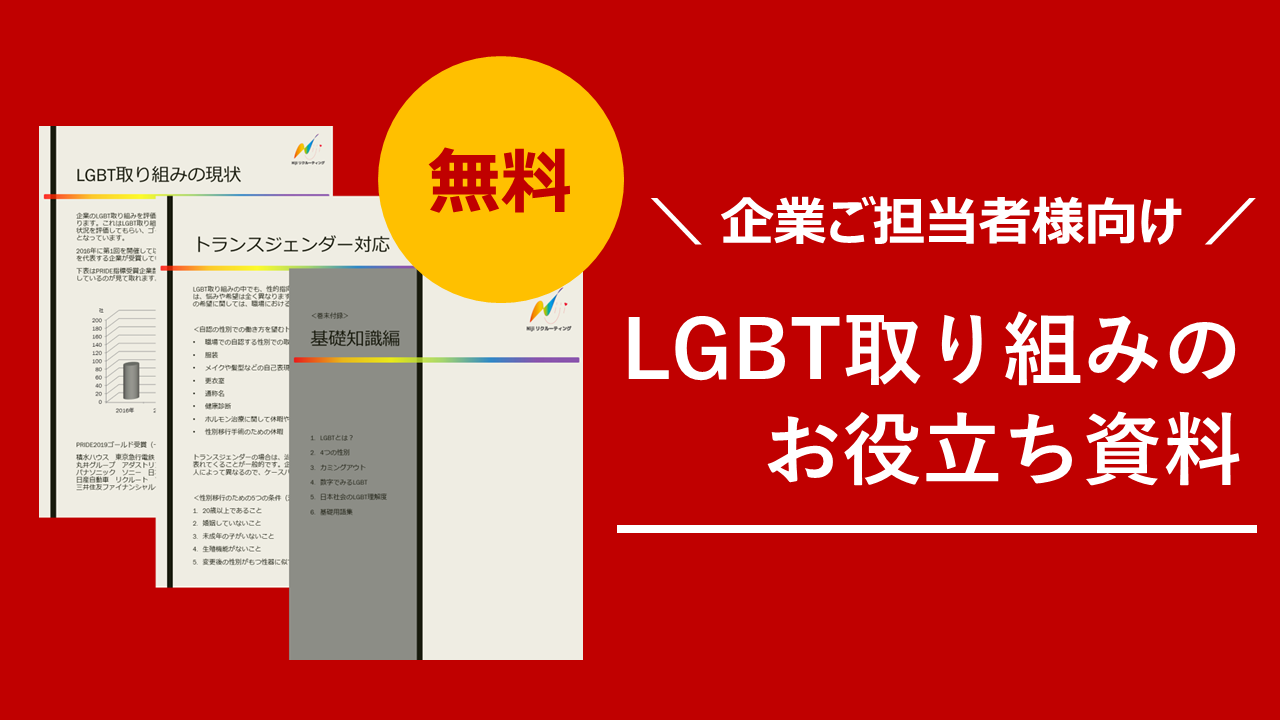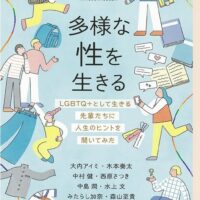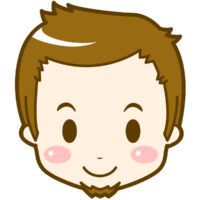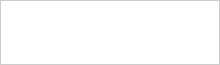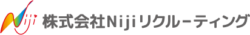性的指向は仕事に直接関係ないため、普段の職場で問題になるケースはそれほど多いわけではありません。
しかし、職場環境、心理的安全性などの点で働きにくさを感じ、それが最大の理由でなくても、きっかけや後押しとなって転職をするケースがあります。
今回は、直接、SOGIハラを受けたわけではありませんが、上長の発言がきっかけとなって退職を決意したAさんの話をご紹介します。
私は30代のプログラマーです。
ゲイであることは親しい友人には伝えていますが、現職の会社ではカミングアウトしていません。
日々の業務そのものに大きな不満はなく、技術的にもやりがいを感じていたのですが、最近になって転職活動を始めました。そのきっかけには、自分がゲイであることと職場の雰囲気が大きく関わっています。ある日、チームの雑談の中で、上長が「最近はどこもダイバーシティやLGBTって話がおおいけれど、正直ちょっとやりすぎかなと思う」と笑いながら言ったことがありました。
私はその場で何も反論しませんでした。
けれども、心の中ではざわつきが止まりませんでした。
「やりすぎ」と言えるほど自分は職場で理解されたことも、配慮されたこともありません。
ただ黙って自分のことを隠しているだけです。
それなのに「配慮が過剰だ」と言われると、強い疎外感を覚えました。この発言は、一回だけではなく、似たような発言は何度かありました。
たぶん発言している上長も、周囲の同僚も特に何も感じていないと思いますが、私はずっと引っかかっています。
この発言は、転職の決定打ではありませんが、「この会社で長く働くのは難しいかもしれない」と思うきっかけにはなりました。私はこれまで、あえてカミングアウトをしてきませんでした。
理由はシンプルで、仕事の成果とセクシュアリティは関係ないと考えていたからです。
けれど、カミングアウトをしていないからといって、差別的な発言や偏見から完全に守られるわけではありません。
むしろ「いないもの」として扱われることによる孤独感のほうが強いと感じています。一方で、転職活動を進めるにあたり、「では次の会社ではLGBTの理解度やカミングアウトして働ける環境が最優先か?」と自問します。
正直、それも違うように感じています。LGBTの理解度は会社ごとに大きく異なりますが、外部からはなかなか分からないからです。企業がどれだけ制度を整えても、現場の空気や上司の一言で雰囲気は大きく変わります。
私が今の職場で感じたことがまさにそうでした。
パンフレットやホームページに「LGBTフレンドリー」と書かれていても、実際に働く現場で同僚がどんな反応をするのかは、外からは見えません。
だからこそ、就職先の理解度は重要ではあるけれど、判断材料としては不確かだと感じています。私はプログラマーとしてスキルアップを望んでいます。
もっと新しい技術を学びたいし、大きなプロジェクトにも挑戦したい。
そのためには、仕事内容は一番大切ですが、同時に職場の空気に気を取られず、集中して仕事ができる場所に身を置くことも不可欠だと思っています。
「理解度」は決め手にはならないけれど、「理解のなさ」は辞める動機やきっかけになるような気がします。
Aさんは現在、転職活動中で、現職にはすでに退職の相談もしています。
現職の退職理由はキャリアアップをしたいから、という理由だけでセクシュアリティに関することは一切話していないそうです。
Aさんは、職場の上長の発言は“ハラスメント”とまでは受け止めていませんでしたし、また簡単に解決できることでもないと思って、職場のハラスメントホットラインなどの相談窓口にも相談はしていませんでした。
このようなケースでの人事部門としての対応は簡単ではないのですが、このような事例は少なくないので、職場づくりのヒントにしていただければと思います。