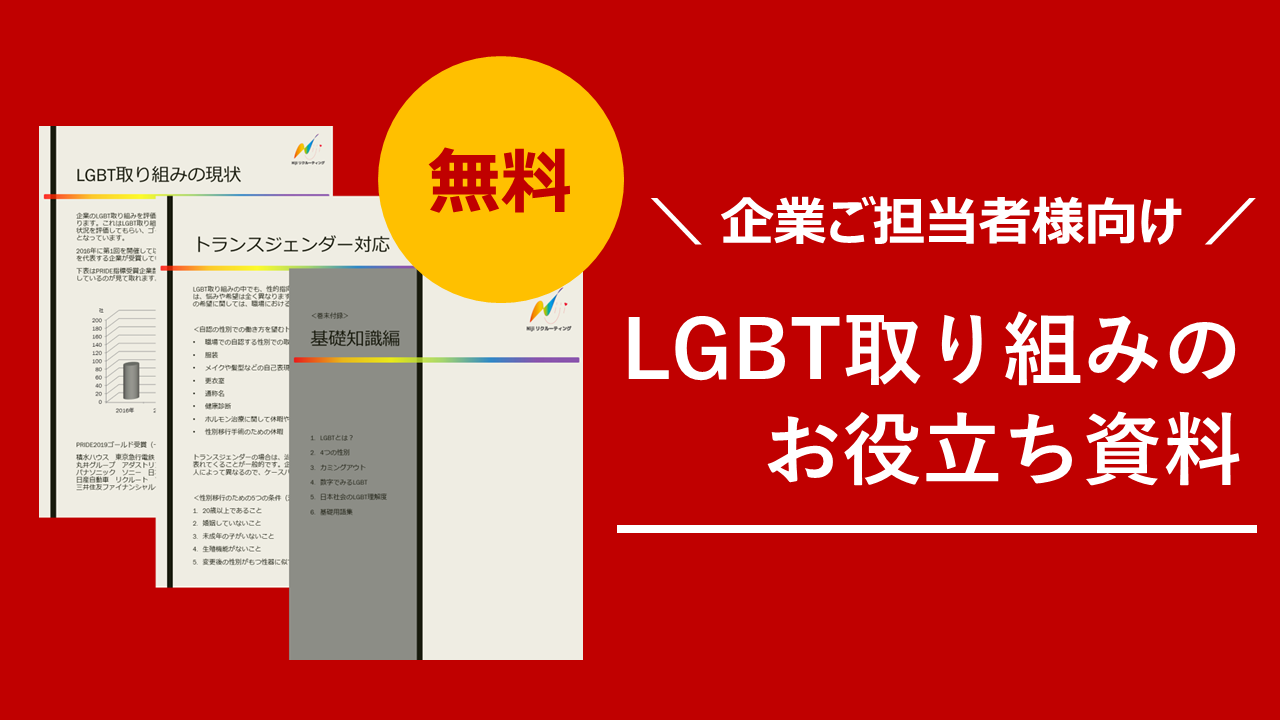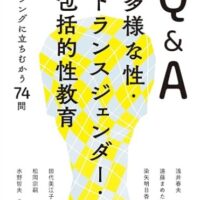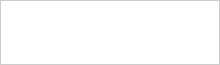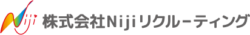企業におけるLGBT関連の取り組みは、この数年で大きく進展しました。
同性パートナーシップ制度の導入や福利厚生の見直し、多様な人が利用しやすいトイレや更衣室の設置など、制度や設備の整備は人事部を中心に比較的スピーディーに進められます。
しかし、本当の意味で働きやすさを実現するには「制度」や「設備」だけでは足りません。
時間はかかるけれど、もっとも重要なのが「風土」の部分です。
この難しい風土づくりはどのように進めるのが良いのでしょうか?
風土とはつまり「職場の理解」です。
日々のコミュニケーションや雰囲気の中に、多様性を受け止める感覚が自然と根づいているかどうか。これがあるかないかで、社員が安心して自分らしく働けるかどうかが大きく変わってきます。
多くの企業ではまず「LGBT基礎研修(eラーニング)」からスタートします。
性的指向や性自認に関する基本用語を学び、アウティング(本人の同意なく性的指向や性自認を暴露すること)が禁止であることを確認する。
これはとても大切な第一歩です。
しかし、ここで注意すべきなのは「知識」と「理解」は同じではないということです。
たとえば「アウティングはしてはいけない」と知識として覚えていても、現場でうっかり繰り返されてしまうことがあります。
これは知識がないのではなく「自分事化」できていない、つまり意識の問題です。
「頭ではわかっているけれど、心の中ではまだ実感がない」状態が続くと、行動に結びつきません。
だからこそ、企業の次のステップは「知識をどう理解につなげるか」という工夫になります。
職場の風土を育てる方法は、大きく二つの方向があります。
一つは「アライ(LGBTを理解・支援する人)を増やす」ことです。全員が完璧に理解していなくても、声をあげられる人、寄り添える人が一定数いるだけで安心感はぐっと高まります。
アライを増やすには、研修だけでなく、社内啓発週間や情報発信、アライを可視化するステッカーやバッジなども効果的です。
もう一つは「全員の知識と意識を少しずつ深めていく」ことです。
これは時間がかかりますが、職場の基盤を強くするためには欠かせません。
そのためには、LGBTに関する情報に触れる機会を増やすことがポイントです。
1回研修を受けただけでは知識はすぐに薄れてしまいます。頻度高く、さまざまな人の声を耳にすることで、「他人事」だったテーマが次第に「自分事」として理解されるようになります。
LGBTに関する取り組みを進める中では、ときに否定的な意見や戸惑いの声も上がります。
これを一律に「不適切」として排除するのではなく、職場で共有し、どう考えるかを話し合う場を持つことも理解を深めるきっかけになります。
他者の価値観に触れることで「自分はこう思うけれど、相手はなぜそう感じるのだろう」と考えるきっかけになり、結果として職場全体の理解が進んでいきます。
大切なのは「正しい知識」だけを積み上げるのではなく、さまざまな声が存在する現実を見つめることです。
そこから学びを深めることが、風土づくりにつながります。
では基礎研修の次の研修として具体的にどんな取り組みがあるでしょうか?
「もう基礎研修は済んだから、次は応用に進もう」という声もありますが、基礎知識を繰り返し学ぶことには大きな意味があります。
人は一度聞いただけでは覚えきれませんし、知識は時間が経つと忘れてしまいます。
また、同じ内容でも違う角度や事例で語られると、新たな気づきが生まれるものです。
さらに基礎的なことの理解なくして、応用(より深い事例など)をお話ししてもなかなか伝わりにくいのが現実です。
浅く広い話を少し違う角度から説明する研修にしたり、あるいは特定のテーマ(トランスジェンダーの働き方とか、採用における注意点など)を深堀することで次のステップとする方法も考えられます。
さらに、知識を一方的にインプットするだけでなく、すでに学んだ内容について社員同士でディスカッションする場を設けることも効果的です。
お互いの考えや価値観を共有することで、理解はぐっと深まります。
制度や設備は、導入すれば比較的短期間で成果が見えます。
しかし、風土づくりはそうはいきません。社員一人ひとりが少しずつ理解を深め、行動に結びつけていくには、時間もエネルギーも必要です。
けれど、それは「時間をかける価値がある投資」です。
LGBTに限らず、多様性を尊重する風土が根づいた職場は、誰にとっても安心して働ける場所になります。
そのための次の一歩は、基礎研修を終えた後に、知識を理解へ、そして行動へとつなげる工夫を重ねていくことです。