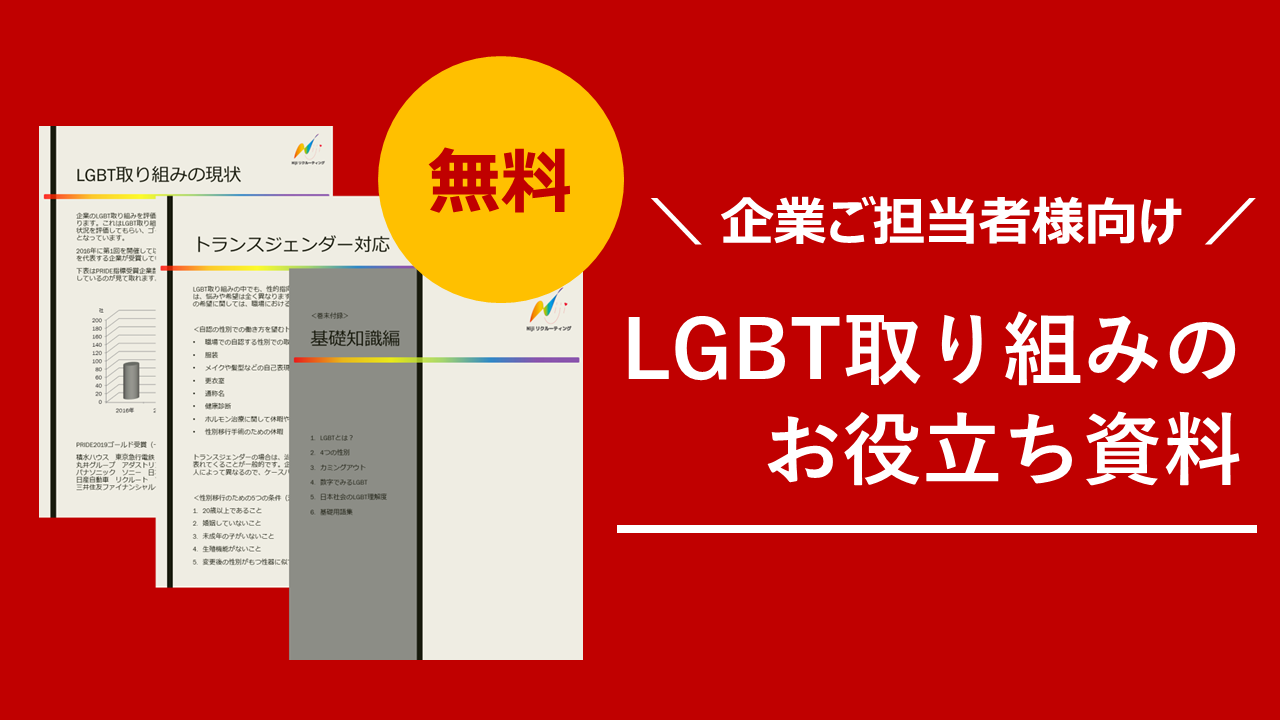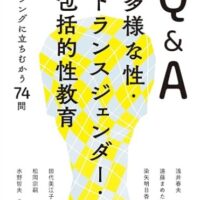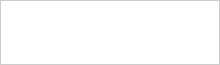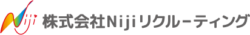LGBTに関する研修やダイバーシティ推進が進むなかで、差別は昔と違ってなくなってきており、働きやすくなっているのでは?という声を耳にすることがあります。
確かに、露骨な差別発言や採用での明示的な排除など、法的に問題となるような行為は減ってきています。
そういう点では、LGBT当事者が働きやすくなっている面は確かにあります。
一方で、それでもLGBT当事者の多くが「働きにくさ」を感じているのが現実です。
その背景には、差別には至らないものの、より日常的で見えにくい「マイクロアグレッション」の存在があります。
差別とマイクロアグレッションはどのように違うのでしょうか?
差別とは、特定の属性を理由に機会や待遇を不当に制限することです。
- トランスジェンダー社員に対し、トイレの利用を制限する
- 採用面接で「結婚予定は?」「将来子どもは?」と性的指向や性別役割を前提にした質問をする
- 福利厚生の配偶者手当や育児休暇を異性愛カップルに限定する
これらは意図の有無にかかわらず、制度的・行動的な差別と考えられます。
企業の人事としては、これらは制度・規程の見直しで是正できる領域といえます。
しかし、「働きにくさ」はこうした明示的な差別だけでは説明できません。
マイクロアグレッションとは、悪意なく発せられる小さな言動が、当事者に心理的な負担や疎外感を与えることを指します。
一つひとつは軽く見えても、日々の積み重ねが心をすり減らします。
たとえばこんな場面です。
- 「うちの職場にはゲイの人いないよね」と雑談で言われる
- 席順など男女で区別する
- 何気ない会話の中で「彼氏(彼女)いるの?」と異性を前提に聞かれる
- カミングアウトした社員に「全然気にしないよ!」「そういう人も好きだよ」と過剰に反応される
- 「LGBTって最近、流行っているよね」と言われる
これらの多くは「悪気がない」言葉です。
けれど当事者にとっては、「自分が“普通”ではない」というメッセージとして積み重なり、職場で安心して自分を出すことを難しくする場合があります。
マイクロアグレッションの厄介な点は、発言した側が自覚しにくいことにあります。
そのため、受け手が違和感を覚えても、「気にしすぎかも」「場の空気を壊したくない」と飲み込んでしまうことにつながります。
沈黙が積み重なるうちに、職場には“表面上の調和”が保たれ、内側で当事者の孤立が進むことがあります。
マイクロアグレッションを減らすために、どうするのがいいでしょうか?
「言葉を選ぼう」と言われることがあります。
確かに、「彼氏・彼女」ではなく「パートナー」と言い換える、「男/女」以外の選択肢を設ける──こうした工夫は入口として大切です。
しかし、それだけでは表面的な対応にとどまります。
なぜその言葉が相手を排除してしまうのかを理解しなければ、根本的な変化は起きません。
大事なのは、自分の中の“当たり前”を問い直す意識です。
「無意識の前提」に気づくことが、マイクロアグレッションを防ぐ第一歩になります。
意識を変えるとは、LGBTの知識を増やすことではなく、「自分の“普通”が誰かにとっては壁かもしれない」と気づき続けることです。
それが、制度や言葉を超えた、風土の変革につながっていきます。
差別をなくすことは出発点として大切です。
その先にあるインクルーシブな職場とは、誰もが自分らしさを隠さずに働ける環境です。その実現には、「見えない壁」に気づき、日々の小さな違和感を共有できる文化が欠かせません。
マイクロアグレッションの存在を正しく理解し、組織として学び合う姿勢を持つことが、LGBTに限らず多様な人材が力を発揮できる職場づくりの基盤となりえると考えられます。